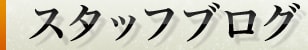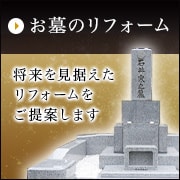- 株式会社石徳
- スタッフブログ
北海道のお客様
北海道にお住まいですが、お子様が都内在住なので、お墓は都内にというお客様とご縁をいただきました。北海道と東京と遠距離ではございますが、メールや電話でやり取りを重ね無事にお墓が完成し、お引渡しいたしました。お引渡し時に北海道のお土産を頂戴いたしました。

お心遣いに感謝申し上げます。社員一同で美味しくいただきました。
筆供養
先日、出入りのお寺様で「筆供養」が行われていました。

「筆供養」とは、役目を終えた筆に感謝し、筆作りのために毛を提供してくれた動物達の供養を行うとともに書道の上達を願い浄火の中に筆を投じる行事のことです。

筆塚では煙があがり、お経が響いています。この煙をかぶると字が上手くなると言われております。

だらだら祭り
事務所からほど近い「芝大神宮」にお参りしてきました。

芝大神宮は、伊勢神宮の神様をお祀りしていることから、「関東のお伊勢さま」と呼ばれています。縁結び・強運(ごううん)・商売繁盛のご利益があるとされている東京のパワースポットの一つです。
芝大神宮では9/11~9/21の間、例大祭が行われておりました。
芝大神宮の例大祭は、11日間「だらだら」と行われるため「だらだら祭り」とも呼ばれており、期間中は多くの人で賑わいます。

文化2年(1805年)2月、芝大神宮の境内で起こった「め組の喧嘩」に由来してか、狛犬の足元には「め組」の彫刻がありました。

16基の御神輿が集まる「神輿渡御」は既に終わっておりましたが、年内を穏やかに過ごせるよう、お伊勢様に手を合わせることができました。
寝釈迦様
先日珍しい寝釈迦様にお会いしました。
寝釈迦様とは、お釈迦様入滅のときの寝姿のことを言うようですが・・・
気持ちよさそうにリラックスしております。

こちらはレプリカのようです。江戸時代頃に制作されているご本尊様は、寝釈迦様の奥の看板に直線距離で6キロと書いてありますが、登山口から徒歩で約1時間半ほどの険しい急斜面の山道を登った先にいらっしゃるそうです。
東の奥参り
東の奥参りに行って参りました。
古くから、西の伊勢神宮に詣でることを「西の伊勢参り」、東の出羽三山に詣でることを「東の奥参り」と言い、双方を詣でることは重要な人生儀礼のひとつとされていました。出羽三山は、山形県鶴岡市にある羽黒山、月山、湯殿山の総称で、千四百年以上前に開かれました。羽黒山が現世、月山が前世、湯殿山が来世という三世の浄土を表し、羽黒山→月山→湯殿山の順の巡礼が一般的です。

まずは、羽黒山に参拝して参りました。

羽黒山は、数々の文化財があり、五重塔は国宝です。現在の塔は長慶天皇の文中年間(約600年前)庄内の領主で、羽黒山の別当であった武藤政氏の再建と伝えられています。

羽黒山の山頂にある出羽三山神社には、三山の神々が祀られています。それは月山や湯殿山が冬季は雪で参拝も祭典を行うこともできないので、三山の祭典はすべてここで執り行うためです。ここを参拝すれば三山を巡ったことになるとされる所以です。現在の社殿は文政元年(1818年、江戸時代)に再建されたもので、萱葺の建造物としては日本最大の大きさです。

続いて湯殿山の参拝に行って参りました。

湯殿山神社は古来より「語るなかれ」「聞くなかれ」と戒められ、写真撮影も禁止されています。
松尾芭蕉もこの地を訪れましたが、この戒めに従い、奥の細道の中でも多く語ってはいません。「語られぬ湯殿に濡れる袂かな」この句を残しているのみです。
大変神聖な場所で大変神秘的な参拝をして参りました。
残念ながら「月山」への参拝は叶いませんでしたが、神様の山を参拝しパワーを頂いて参りました。
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年6月
- 2015年3月