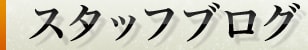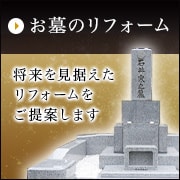- 株式会社石徳
- スタッフブログ
夏バテ防止
本日は予想最高気温37°ですが、炎天下の中、お墓を設計するために出入りのお寺様にてお墓の寸法を
測って参りました。連日の猛暑に負けず、夏バテ防止のため、ランチに天ぷらをいただきました。

予報によると、今年の8月は全国的に平年より暑いそうです。
健康にはくれぐれもご留意くださいませ。
盆踊り
長かった梅雨もようやく明け、いよいよ夏本番となりました。
本日、出入りのお寺様へお伺いしたところ、盆踊りの準備が始まっていました。

盆踊りは約500年の歴史があり、本来はお盆の時期に死者を供養するための行事で、ご先祖様の霊を迎え入れて、また送るための風習に発したものとされています。今年の盆踊りは、ご先祖様へ思いをはせ参加してみてはいかがでしょうか。
歓迎会
先日、新しいスタッフの歓迎会を行いました。
皆で美味しいランチをいただき、

デザートにはケーキを。


しっかり栄養を摂って、皆で暑い夏を乗り切りたいと思います。
こだわりの本小松石自然石のお墓が完成しました。
こだわりの本小松石青手自然石のお墓が完成しました。神奈川県真鶴町にある採石場に何度も足を運び、石の選定から始まり、デザインを作成し、打ち合わせを重ね、こだわり抜いたお墓が完成しました。
▼石の選定(神奈川県真鶴町 本小松石採石場)


▼完成予想図CG

▼完成予想図CG(現地写真との合成)

▼完成イメージ図
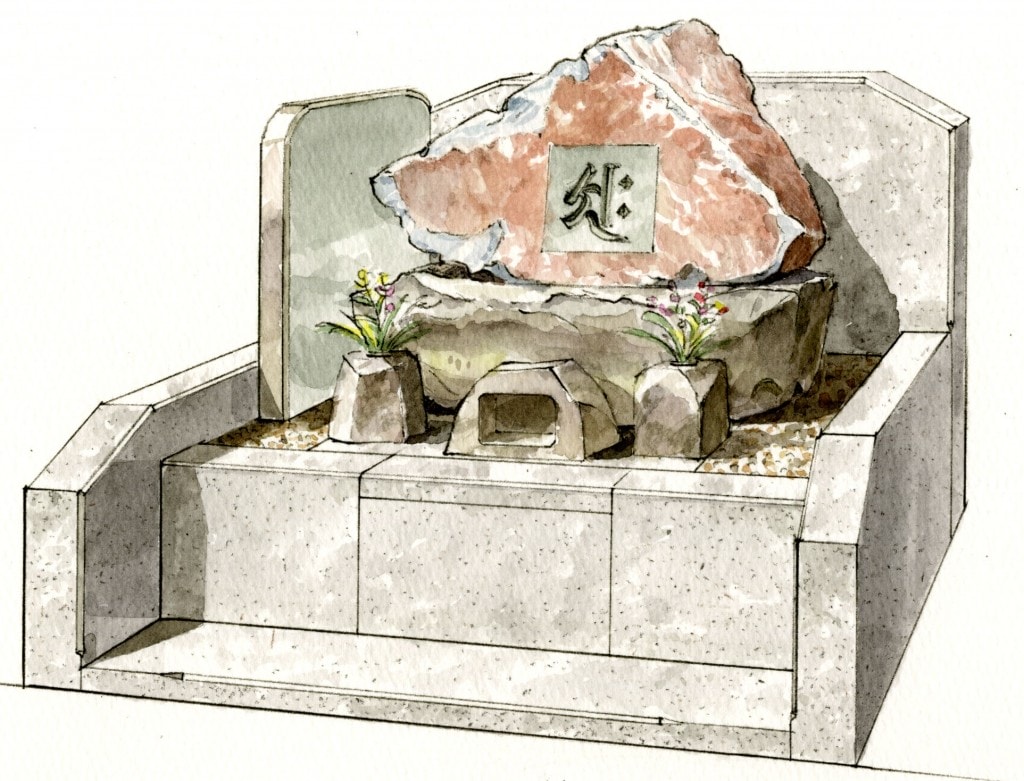
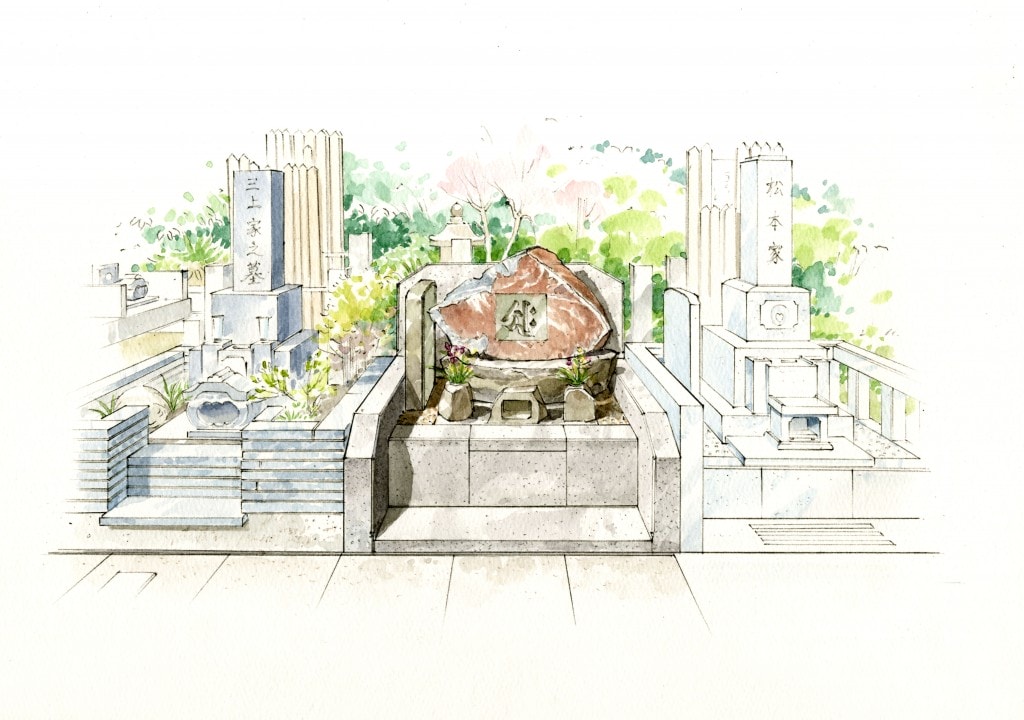
▼加工

▼彫刻(薬研彫り)

▼施工

▼完成


この世で唯一無二のお墓ですが、決して目立ち過ぎず周囲との調和がとれた、上品でどっしりと立派なお墓に仕上がりました。お施主様にも大変喜んでいただきました。
世界にただ一つのお墓をお探しでしたら、是非ご用命ください。
詳しくは、建墓例をご覧下さいませ。
烏森神社夏越大祓
今、弊社近くの烏森神社では夏越大祓(なごしのおおはらえ)という神事が行われています。
この期間は特別な御朱印がいただけるということで、今日も朝早くから行列が出来ていました。
この神事には、半年間知らず知らずのうちに積もってしまった罪穢れを
「芽の輪」という大きな輪をくぐることによって祓い清め、
残りの半年の無病息災を祈願する、という意味が込められているそうです。

アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年6月
- 2015年3月